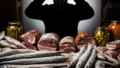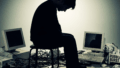他人が強欲になっているときは恐る恐る、周りが怖がっているときには貪欲に
これは、「オマハの賢人」として世界中の投資家から尊敬を集めるウォーレン・バフェットが説いた、最も有名な投資格言の一つです。平たく言えば、
「市場が熱狂している(株価が高騰している)ときには慎重に売り、市場が恐怖に包まれている(株価が暴落している)ときには積極的に買う」
という意味になります。
この言葉は、安く買って高く売るという商売の基本原則を投資に当てはめたものであり、そのシンプルさゆえに、投資の本質を鋭く突いています。理論上、これを完璧に実行できれば、誰でも莫大な富を築けるはずです。しかし、現実には「言うは易く、行うは難し」の典型例として知られています。
なぜ、私たちは頭では理解していながら、暴落の恐怖に駆られて投げ売りし、バブルの熱狂に乗って高値掴みをしてしまうのでしょうか。
本記事では、このバフェットの黄金律を実践することがなぜこれほどまでに困難なのか、その背景にある人間の心理、市場の構造、そして実践的な課題を深掘りし、その上で私たちがどうすればこの難題を克服し、賢明な投資家へと成長できるのかを探っていきます。
第1部:「恐怖で買う」ことが難しい理由
市場が恐怖に覆われる局面とは、具体的には経済危機や金融ショックによる株価の暴落時を指します。リーマンショック、コロナショックといった歴史的な暴落を思い浮かべれば、その異様な雰囲気は想像に難くないでしょう。このような状況で「買う」という行為は、なぜこれほどまでに難しいのでしょうか。
1. 人間の本能的な心理障壁
私たちの脳には、石器時代から受け継がれてきた生存本能が深く刻まれており、それが現代の金融市場において不合理な判断を引き起こす原因となります。
プロスペクト理論と損失回避性
行動経済学の父、ダニエル・カーネマンが提唱した「プロスペクト理論」は、この謎を解く鍵となります。この理論によれば、人間は「利益を得る喜び」よりも「損失を被る苦痛」を2倍以上も強く感じるとされています。
株価が暴落している局面では、保有資産の価値が日々失われていくという強烈な「痛み」を経験します。この痛みを前に、「さらに下落して、もっと大きな損失を被るかもしれない」という恐怖が、「将来の値上がりで得られるかもしれない利益の喜び」を圧倒してしまうのです。
その結果、合理的な判断である「安く買う」という選択ではなく、これ以上の痛みを避けようとする本能的な反応として「投げ売りする(損切りする)」という行動に走りがちになります。底値圏で買うということは、この強烈な痛みに正面から向き合い、さらに損失が膨らむリスクを受け入れる覚悟を意味するため、心理的なハードルが極めて高いのです。
ハーディング効果(群集心理)
人間は社会的な動物であり、集団から孤立することを恐れる本能があります。市場がパニックに陥ると、大多数の投資家が一斉に売り注文を出します。テレビやネットニュースは連日「株価大暴落」の文字を躍らせ、専門家たちは悲観的な見通しを語ります。
このような状況下で、自分だけが群衆と逆の方向、つまり「買い」に向かうことは、とてつもない精神的なプレッシャーを伴います。
「皆が売っているのだから、売るのが正しいに違いない」
「自分だけが知らない、もっと深刻な何かがあるのではないか」
という不安が頭をよぎり、多数派の行動に同調してしまうのです。これがハーディング効果(群集心理)であり、恐怖の連鎖を加速させ、セリング・クライマックス(売りが最高潮に達する局面)を生み出す大きな要因です。
2. 情報環境がもたらす認知バイアス
暴落時には、私たちを取り巻く情報環境もまた、冷静な判断を著しく妨げます。
ネガティブ・ニュースの洪水
メディアは本質的に、人々の関心を引く悲観的なニュースを好んで報道する傾向があります。暴落時には、失業率の悪化、企業の倒産、先行きの不透明感を煽る見出しが溢れかえります。
こうしたネガティブな情報のシャワーを浴び続けると、あたかも世界経済が二度と立ち直れないかのような錯覚に陥り、企業の本来の価値や長期的な成長性といった、投資判断で最も重要な要素を見失ってしまいます。
「今回は違う」という幻想
歴史を振り返れば、市場は幾度となく暴落を経験し、その都度、時間をかけて回復し、史上最高値を更新してきました。しかし、暴落の渦中にいると、
「今回は過去のケースとは違う。もっと深刻だ」
という言説が必ずと言っていいほど現れます。ITバブル崩壊時には
「新しい経済は幻想だった」
と言われ、リーマンショック時には
「資本主義の終わり」
すら囁かれました。このような「今回は違う」論は、過去の教訓から学ぶことを妨げ、恐怖を正当化する強力な材料となってしまうのです。
3. 実践的な困難さ
心理的な障壁を乗り越え、いざ「恐怖で買おう」と決意しても、そこには実践的な壁が立ちはだかります。
「底値」は誰にも分からない
最大の恐怖が市場を覆っているときが絶好の買い場であることは、後からチャートを見れば一目瞭然です。しかし、リアルタイムでその瞬間にいる投資家にとって、「今が底値なのか」を判断することは不可能です。
「落ちてくるナイフは掴むな」という格言があるように、あまりに早く買い向かえば、さらなる下落に巻き込まれ、大きな評価損を抱えることになります。この「底値当ての難しさ」が、買いのタイミングを躊躇させ、結果的にチャンスを逃すことにつながるのです。
投資余力(キャッシュ)の枯渇
そもそも、暴落時に買うためには、その原資となる現金(ドライパウダー)を保有している必要があります。しかし、多くの個人投資家は、好調な相場で利益機会を逃したくないという思いから、常に資金の大部分を株式に投じている「フルインベストメント」に近い状態にあります。
いざ絶好の買い場が訪れたときには、追加投資する余力が残っておらず、指をくわえて見ているしかない、というケースは決して少なくありません。
第2部:「熱狂で売る」ことが難しい理由
「恐怖で買う」ことの対極にある「熱狂で売る」こともまた、同様に、あるいはそれ以上に難しい判断です。市場が熱狂に包まれるバブル期には、誰もが浮かれ、株価は永遠に上がり続けるかのような錯覚に陥ります。
1. 「強欲」という抗いがたい感情
恐怖が暴落時の行動を支配する感情だとすれば、熱狂時の支配的な感情は「強欲(Greed)」です。
「もっと上がるはずだ」という期待
保有している株の価格が日々上昇し、含み益がみるみる膨らんでいく状況は、何物にも代えがたい高揚感をもたらします。このとき、合理的な判断(=割高になったので利益を確定する)をしようとしても、「ここで売ったら、その後のさらなる上昇を取り逃してしまうのではないか」という強欲が頭をもたげます。
この「乗り遅れることへの恐怖(FOMO – Fear of Missing Out)」は強烈で、適正な株価水準を遥かに超えてもなお、人々を買いに走らせ、売りを躊躇させるのです。
後悔回避と保有効果
もし売却した後に、その株がさらに高騰した場合、「売らなければもっと儲かったのに」という強烈な「後悔」を経験することになります。人間はこの後悔を極端に嫌うため、利益確定の決断を先延ばしにする傾向があります。
また、自分が長く保有している銘柄に対しては、「保有効果」と呼ばれる心理バイアスが働き、客観的な価値以上に過大評価してしまいがちです。「この会社には将来性がある」「自分は慧眼だった」といった思い入れが、冷静な売却判断を鈍らせるのです。
2. 熱狂を正当化する情報環境
バブル期には、市場の熱狂をさらに煽るような情報が社会に蔓延します。
楽観論の蔓延と新たな物語
市場が熱狂しているときは、メディアもアナリストも強気一色になります。「目標株価の大幅な引き上げ」や「景気拡大はまだまだ続く」といった楽観的な見通しが溢れかえります。
さらに、その熱狂を正当化するための「新たな物語(ニュー・エコノミー、パラダイムシフト)」が語られます。ITバブルの際には
「インターネットが世界を変え、従来の株価評価指標はもはや通用しない」
とされ、近年のEV(電気自動車)ブームでも同様の言説が見られました。こうした物語は、現在の高すぎる株価を「新しい時代の到来」として正当化し、投資家に「今回は違う」と信じ込ませることで、バブルをさらに延命させる役割を果たします。
3. 実践的な困難さ
「天井」も誰にも分からない
暴落時の「底値」と同様に、熱狂の頂点である「天井」を正確に予測することもまた不可能です。あまりに早く売却してしまえば、その後の大きな上昇相場を逃すことになり、「機会損失」という後悔を味わうことになります。
バフェット自身も、
天井で売り抜けようとするのは愚か者のやることだ
と語っており、ピークを正確に当てることの不可能性を示唆しています。この「天井当ての難しさ」が、多くの投資家をバブル崩壊のその瞬間まで市場に留まらせる原因となるのです。
第3部:では、どうすれば克服できるのか?
「恐怖」と「強欲」という人間の本能に根差し、市場の情報環境によって増幅されるこれらの困難を、私たちはどうすれば乗り越えることができるのでしょうか。完璧な実践は不可能かもしれませんが、その原則に近づくための方法は存在します。
1. 規律とルールの設定
感情に流されないための最大の武器は、あらかじめ「規律」と「ルール」を設けておくことです。
- 明確な投資哲学を持つ:「自分はなぜ投資をするのか」「どのような価値基準で銘柄を選ぶのか」という確固たる軸を持つことが、市場のノイズに惑わされないための土台となります。バフェットにとってのそれは「優れたビジネスを、公正な価格で買う」という哲学でした。
- 売買ルールの事前設定:感情が判断を曇らせる前に、冷静な頭で売買のルールを決めておきます。例えば、「購入時の株価から〇%下落したら、〇%買い増す」「PER(株価収益率)が過去の平均を大幅に上回る〇倍に達したら、保有株の3分の1を売却する」といった具体的な数値目標です。
- 機械的な実行:一度決めたルールは、市場がどのような状況になろうとも、感情を排して機械的に実行します。毎月一定額を積み立てる「ドルコスト平均法」は、まさにこの規律をシステム化したものであり、高値掴みを避け、安値で多く買うことを自動的に実現してくれる優れた手法です。
2. 長期的な視点と歴史からの学び
短期的な株価の変動に一喜一憂するのではなく、常に長期的な視点を維持することが重要です。
- 企業のオーナーになる意識:株を買うことは、その企業の一部のオーナーになることです。日々の株価ではなく、その企業の製品やサービス、競争力、収益性といった本源的価値(ファンダメンタルズ)に焦点を当てることで、市場の狂騒から一歩引いて冷静に状況を評価できます。
- 歴史に学ぶ:過去に起きた何度も繰り返されるバブルと暴落の歴史を学ぶことは、最高の教科書となります。チューリップ・バブルから南海泡沫事件、ITバブル、リーマンショックに至るまで、熱狂と恐怖のパターンが驚くほど似通っていることに気づくでしょう。歴史を知ることで、現在の市場がサイクルのどの位置にあるのかを客観的に推測し、「今回は違う」という幻想に惑わされにくくなります。
3. 逆張り投資家としての覚悟
バフェットの格言は、本質的に「逆張り(コントラリアン)」の思想です。これは、大多数の意見や行動と逆のポジションを取ることを意味し、精神的な強さを要求されます。
- 孤独を受け入れる:群衆と違う道を行くことは、孤独であり、時には周囲から「間違っている」と非難されるかもしれません。その孤独とプレッシャーに耐え、「多数派が常に正しいとは限らない」という確信を持つ覚悟が必要です。
結論:自己を律する哲学としてのバフェットの言葉
ウォーレン・バフェットの「恐怖で買い、熱狂で売る」という言葉は、単なる投資テクニックではありません。それは、市場を動かす群集心理の本質を理解し、そして何よりも
自分自身の「恐怖」や「強欲」といった根源的な感情をいかにコントロールするか
という、投資家としての哲学そのものを問いかけるものです。
この黄金律の実践が難しいのは、私たちが合理的な経済人ではなく、感情や本能に突き動かされる生身の人間だからに他なりません。暴落の恐怖も、バブルの高揚感も、あまりにリアルで抗いがたい力を持っています。
しかし、その難しさを理解した上で、自らを律するルールを設け、長期的な視座を持ち、歴史から学び、そして時には孤独を恐れずに逆の道を行く勇気を持つこと。
これらを意識し、実践しようと努力を続けるプロセスそのものが、私たちをより賢明で、より成熟した投資家へと成長させてくれるはずです。
完璧にこなすことはバフェット自身にも不可能です。しかし、この原則を目指して一歩でも近づこうとすることが、長期的な資産形成の成否を分ける、決定的な要因となることは間違いないでしょう。